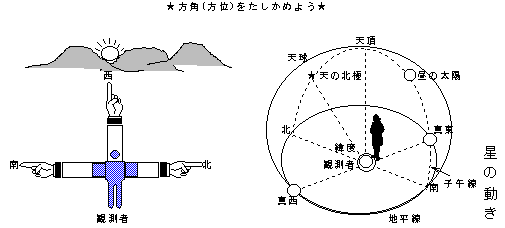
星の動き 星の動きかた
さて、実際に星座をさがす前に、星の動きかたを簡単に説明しましょう。
星はきまった形にならんでいるといいましたが、そのならびかたは変えずに動いています。北のほうにある星は、北極星を中心に、時計の針と反対向きに動きます。それ以外の星は、太陽と同じようにから上って西に沈みます。
星座を見つける準備
星座を見つけるためには、まず東西南北の方向をおおまかに確認しておきましょう。
夕方、太陽が沈む方角が西です。西の方に向かって右手の方向が北、左手の方向が南になります。こうして大体の方向が分かれば、星座をさがす準備はOKです。
★方角(方位)をたしかめよう★
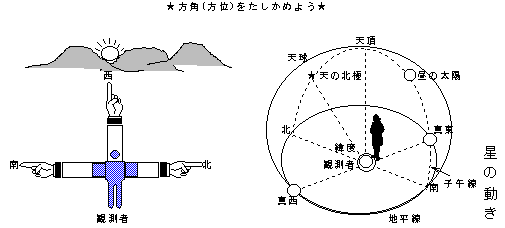
星の動き 星の動きかた
さて、実際に星座をさがす前に、星の動きかたを簡単に説明しましょう。
星はきまった形にならんでいるといいましたが、そのならびかたは変えずに動いています。北のほうにある星は、北極星を中心に、時計の針と反対向きに動きます。それ以外の星は、太陽と同じようにから上って西に沈みます。
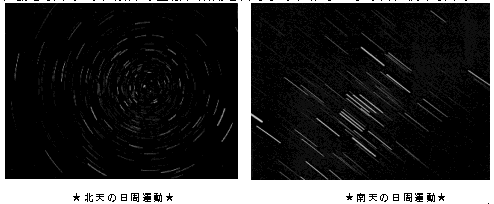
このようにして、星は1日に1回約360度回転します*7。これを、星の日周運動といいます。また、1年を通しても同じような運動を行っています。これを、星の年周運動といいます。
これらの2つの運動のために、見る季節と時間によって、星座の位置が変わってくるのです。
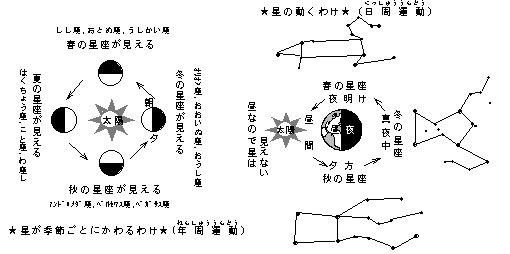
北極星のさがしかた
夜中に方角を正確に知るためには、北極星をさがさなければなりません。
北極星をさがすには、北斗七星を使う方法やカシオペア座を使う方法がありますが、夏の大三角形を使ってもさがすことができます。
ヴェガとデネブをむすんだ線を軸にして、アルタイルを折り返したところに北極星があります。北斗七星やカシオペア座を使った方法ほど正確ではありませんが、夏の大三角形はよく目立つので、覚えておくと便利でしょう。
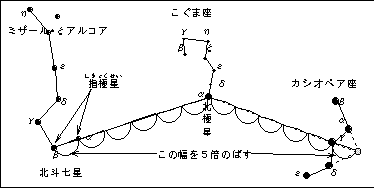
大ぐま座
立春をすぎて暖かくなるところ東北の空にはかの有名な北斗七星が昇ってきます。北斗七星は星座ではなく大ぐま座という星座の腰からしっぽにかけてのほんの一部で、かなり大きい星座です。この北斗七星は指極星としても有名ですが柄の部分の2番目の二等星はミザールと呼ばれています、よく見るとそばに四等星が並んで見えます、この星をアルコアといいその昔アラビアの兵士の視力検査に利用されました。
小ぐま座
あまり名前はなじみがないが、実はこの星座のα星が北極星なのです。ちょうど北斗七星を逆さまにした形をしています。前に北極星は動かないといいましたが実はわずかに移動しています。これは地球の自転軸が太陽や月の引力によりとまりかけたコマのように首ふり運動をするためです。
5,000年前はりゅう座のα星,1,2000年後はこと座のベガにうつります。
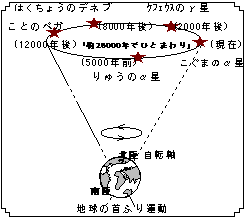
しし座
東の空にはしし座がかに座を追いかけるようにかけ昇ってきます。この星座にはレグルスという白い一等星があります。しし座を探すめじるしはレグルスに向かって伸びる二〜四等星の星が『?』を反対にした形で、ししが頭をもたげた形をしています。また、草刈り鎌に似ている事から“ししの大鎌”とも呼ばれています。ししのしっぽ部分にはデネボラと呼ばれる二等星がありししの姿をかたどっています。なお、このししもヘラクレスに絞め殺された悪いライオンなのです。
しし座全景(画像処理中)
おとめ座・うしかい座
春の星座は大きいものが多いようです。おとめ座、次のうしかい座もそうです。おとめ座は12宮の一つです。この星座にはスピカとよばれる一等星があり“麦の穂”という意味があり、日本では“真珠星”言っていました。また、ソンブレロ星雲(M104)があり見所十分です。うしかい座にはアルクトゥルスといわれる一等星がり大きいひし形をしています。星座の場所は北斗七星の最後の柄の東側にあり割と見つけやしいでしょう。
(画像処理中)
春の大三角形・春のダイヤモンド・春の大曲線
しし座のデネボラ、おとめ座のスピカ、うしかい座のアルクトゥウルスでできる三角形を『春の大三角形』といい、これにりょうけん座コールカルリを加えると『春のダイヤモンド』になります。また北斗七星の柄の部分をアルクトゥウルス方向に延長する線を描きながらおとめのスピカにと向かう大きな曲線を見ることができます、これが『春の大曲線』とよばれています。これらは他のいろいろな星や星座を探すのにすごく便利です。
(画像処理中)
星空を見よう(2)へ(工事中)
Copyright & meilto:m-suto@t-cnet.or.jp
Supported:SEAT(Science Educational Association of Tochigi)栃木科学教育協会