|
第3章 サービスエリア
|
|
「昼飯にしようか」
隊長がパーティ全員の顔を見渡して言った。しかし返事が返ってこない。
大きな岩のかたまりからなる茶臼岳山頂には中アリの大群や家族連れ、おばさんハイカーなどが思い思いに弁当を開け楽しそうに食べている。あやちゃんの目が一点を見たまま動かなくなった。その視線の先を全員が目で追うと、そこにおにぎりがあった。小学校二,三年の男の子が母親の作ってきたおにぎりをうまそうに食べている。
山で食べるおにぎりはなんてうまいのだろう。
日光に鳴蟲山というおもしろい名前の山がある。この山で食べるおにぎりについて、隊長の独身の頃のエピソードがいくつかあるが、この項では書かない。
おにぎりから視線をはずした北川が、ふと我に帰ったかのように、
「隊長、お昼は下に降りてからにしましょう」
北川はきっとビールが飲みたいはずだ。
「1時間もあれば登山口まで下りられる。昼飯は下のそば屋にするか」
隊長も冷えたビールが飲みたい。
「あやちゃん、おにぎりはあきらめて天ざるにしよう」
寺ちゃんも、もちろんグラスでビールだ。
下山して温泉につかり湯上りのビールを飲むことにパーティ全員が意思を一つにしたようである。
峰の茶屋へ向かって下り出すと、ガスのなかに見え隠れする山頂駅からアナウンスが聞こえてきた。
「本日は大変視界が悪くなっております。このアナウンスが聞こえる範囲での散策をお願いいたします」
観光客向けのアナウンスを聞いて、
「冷たいジュースが飲みたい」
突然、マリが言い出した。
「なにを言うてんねん、下までがまんしいや」
北川の声のトーンが高くなった。
「やだ、飲みたい」
「私もコーラが飲みたくなったわ」
ゆかりちゃんまで言い出す。 
「わかった、山頂駅で一服する」
リーダーにはすばやい決断が必要である。
山頂駅は、たくさんの観光客でごったがえしていた。
この那須岳ロープウェイも11月初旬で運行を終え、次の営業再開は翌年の4月からである。
しかし一日1回はメンテナンスのため、通年動かしている。T交通の社員が一週間交替で泊まり込み、日々ロープウェイの管理をしているのである。T交通(株)索道管理部の薄田さんには生涯忘れられない思い出があった。遭難者の遺体搬出である。
薄田さんがまだ20代の頃の話である。
2月中旬の山頂駅宿泊週番のある日、メンテナンス運行を終えた午前11時12分、けたたましい電話のベルが駅事務所に鳴り響いた。
「茶臼岳北面で救助隊が遭難者を発見、3人パーティで1人は遺体、2人は無事。ロープウェイで遺体を下に降ろす依頼が那須警察からあった。1時間ほどで山頂駅に着く予定」
那須山岳救助隊からの緊急電話である。
薄田さんの胸の鼓動が高鳴った。
「遺体の搬出だって!」
もちろん初めての経験である。頭の中が混乱してなにをしたらいいのか、まったくわからない。
ただ、いやな予感がした。
正午を少しまわった時刻、事務所のドアをたたく音で彼は外に飛び出した。
5、6人の男たちが吹雪の中、髪の毛を白くして立っていた。彼はその足元を見た。赤いソリにブルーのシートが被さっている。
「仏さん、乗せてやってくれ」
地元消防団のSさんがにらむように、彼に言った。
何秒かの沈黙のあと、薄田さんが吐くように言った。
「断ります」
「何だと」
「遺体は乗せられません」
「警察から連絡が入っているはずだ」
「このままでは乗せられません」
「このままではだめだと、じゃあどうしたらいいんだ」
「清めの酒を用意して下さい」
「そんなの後でいかんべ」
「ここは私の職場だ。今晩も泊まるし、明日の晩も泊まる」
彼の意思は固かった。押し問答の末、遺体を残し二人の登山者だけをロープウェイに乗せ、下の大丸温泉の土産屋で酒を買って戻ってくるようお願いした。薄田さんのその時の真剣な表情に押され、Sさんも、
「あのときはそれ以上なにも言えなかったんべ」
と述懐していた。
薄田さんも、
「あの日の晩から、ずっと怖くて眠れなかったっぺ」
それはそうだろう。
「あれ以来、毎晩大酒を飲むようになったっぺ」
彼は大きな目を少し優しくして遠くを見つめた。
しかし大酒飲みはそのせいではない。彼の親父さんも晩年は鼻の頭を赤くした大酒飲みだった。
「やっぱりコーラよりジュースのほうがいいネ」
マリも心変わりしている。
山頂から峰の茶屋へ下りて行く途中、中アリたちが5、6人のグループに分かれてゴミ拾いをしていた。地元の中学生のボランティア登山である。
あと30分で登山口、左手に見える朝日岳のアルペン的風貌が少しずつ遠ざかる。
木製の階段を下りると駐車場が見えてきた。
「ふぅ、やっと着いたわ」
ゆかりちゃんのアイシャドーが汗ににじんで薄いパープルからライトブルーに変色しかかっている。下のそば屋まで我慢できず北川が土産屋を指差した。
「わかってる」
本当に酒びたりの山岳会なのだ。
それぞれロング缶を手にした。
「乾杯」
と寺ちゃん、ブシュッ、ウグッ、プァーときた。
殺生石南側の駐車場に車を止め、「鹿の湯」への階段を下りていく。那須の源泉である。
ここの湯は湯船につからないのが原則、頭からかぶるのである。42度から46度まで湯船がいくつかに分かれている。混浴ではない。
夏の温泉にはとんと興味がない隊長は早々に出てきて、湯上りのビールをやっている。
 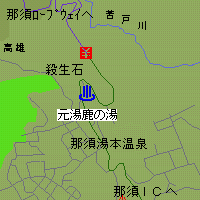
突然、
「隊長、大変、マリちゃんが倒れちゃった」
あやちゃんが洗い髪のまま飛んで来て隊長に言った。
2本目を開け始めた隊長が目を丸くして言った。
「マリが倒れた?どこで」
「湯船につかっていたら、めまいがして、それで床の上に大の字になっているの」
「よっしゃ、すぐ行く」
とも言えず、女湯ののれんの前に立っていたら、50代のおばさんがガラス戸を開けて出て来た。
「最近の娘さんはスタイルがいいね、あれならどこに出しても恥ずかしくないよ」
いったいどこに出すつもりなのだろう。
マリは手ぬぐい1枚を体に乗せて本当に大の字になっているらしい。嫁入り前の娘が素っ裸でしかも大の字になって寝ている光景はセクシーさのかけらもない。マリの性格そのものである。
北川が大笑いして三本目のロング缶を干し上げたところに3人娘が出て来た。
「ごめんなさい。急にめまいがしちゃって」
とマリ。
「46度に長湯すれば、めまいもするわい」
北川が吐き捨てるように言った。
「シャンプーも出来なかったし」
寺ちゃんもぼやいている。
「あんな熱い温泉、初めて」
ゆかりちゃんのほっぺは真っ赤。
「おれも鹿の湯はあんまり好きじゃない、北温泉のほうがいい」
と隊長。
「じゃあ、どうして北温泉に連れて行ってくれなかったの」
マリは責任を隊長に転嫁し始めている。
「あそこは女連れでは二度と行かない」
意味深な隊長の発言、詳細は書かない。

車は東北道を南に向かって走っている。風呂に入ってビールを飲んだら、さすがに疲れが出たらしく女性軍は寝息を立てている。北川が眠そうにハンドルを握る。
「次のサービスエリアで休憩」
隊長が指示。
「ラジャー」
北川が応える。
上河内サービスエリアに入りトイレ休憩。
ベンチに腰掛けてタバコをくわえている隊長と寺ちゃんの前を、帽子を目深にかぶり肩まで伸びた髪を風に揺らせながら通り過ぎた女性がいた。
タバコがまた落ちてしまった。
寺ちゃんの手元から缶コーヒーが離れコンクリートの歩道を転がっていった。
「あの遭難碑のーーー」
と寺ちゃんが言おうとしたが声にならない。
赤のBMWは静かに走り出した。
ほんの数秒の出来事だった。
第4章 血ぬられたテント へ
|
|
|
|