|
第4章 血ぬられたテント
|
|
|
|
県庁前交差点の渋滞が始まっている。
7時半からのミーティングなので玲子は昨夜はいつもより早く床についたが目が覚めたのは6時を20分も過ぎてからだった。
(どうして週の初めに早朝ミーティングなんかやるのかしら)
月曜日の朝はまだ体が会社になじんでいない。
オンライン株取引の説明会である。
玲子の勤めるC証券も10月1日からの株式売買の手数料自由化にともない本格的にオンライン取引に参入してきた。しかし、まだ慣れていない。
先週金曜日に起きたトラブルが社内の緊張をいっきに高めた。
顧客からの前夜のオンライン注文が前場寄り付き前に発注されてしまい寄り付きで買いがさばかれてしまった。オンラインならば当然、そうなるのだがネット売買に不慣れな顧客は納得しない。今朝のミーティングは相場が寄った段階での成立株価の違いの説明会である。
「そこから3クリックになります」
加藤がログインの混雑を説明している。
しかし玲子は画面を見ていない。
(この人、いくつになるのかしら)
茶のフレームのメガネが角張ったあごに似合っていた。
「相場の上昇局面での操作に注意して下さい」
慣れた口調である。この種の説明会はC証券で三社目。
(先週のN証券のほうが、やはりレベルが高いな)
加藤の率直な印象である。
玲子はよく動く加藤の口元をぼんやりと見ていた。
「お疲れ様でした」
開店10分前に説明会は終わった。給湯室に行こうとした玲子に加藤が声をかけて来た。
「来週の連休に中原の好きだった白馬に登るけど、一緒に来ませんか」
仕事の時の表情とは一変して柔和な顔になっている。
中原と加藤は同じ社会人山岳会に属していた。
加藤のほうが中原より五つ年上になるが二人は気が合った。
玲子が中原の所属する山岳会のメンバーと初めて登った山が尾瀬の至仏山だった。
その時のメンバーの中に加藤がいた。玲子は大勢の山男に囲まれて初めての本格的な登山だった。メンバーの名前と顔が一致しないまま下山して来たが、加藤は長い髪と、いつも遠くを見るような眼差しをする玲子を覚えていた。
10月9日午前5時、隊長の家の前にパジェロが止まった。
まだ真っ暗である。
「おはようございます」
福井さんの奥さんが車から降りて笑顔で挨拶をした。
「早くて申し訳ありません」
45リッターのザックを乗せながら隊長が恐縮する。
「じゃあ、運転替わって下さい」
夜勤明けの戸部厚が挨拶もそこそこに助手席に移動した。
妻と長男はまだ深い眠りの中、ハンドルを握った隊長はまるでスペースシャトルのパイロットにでもなった気分で晴れやかにアクセルを踏み込んだ。
やはり上信越道は詰まる。碓氷軽井沢の二つ目のトンネルで車は止まった。
寺ちゃんの忠告どおり早めに出発したのだが、三連休の初日、紅葉の信州への道は混まないはずがない。
「グゥー、スゥー、グガッ」
しかし福井さんはよく眠る男だ。宵っ張りの朝寝坊である。
毎朝、会社のタイムカードを1分前に押すという神業を身につけている。
9時半に長野インターに着き、丹波島橋をむ左折、オリンピック道路から見える真っ白な鹿島槍が福井さんの目を一気に醒ましてくれる。
148号線を北上し栂池の駐車場についたのは11時半、珍しく時間厳守で全員集合となった。
荷の分配は隊長の仕事、リーダーの公平性が試される。
「あっ、ずるい」
「缶詰が多すぎる」
「水筒が二つも」
隊長の命令は絶対なのである。
12時25分にロープウェイ頂上駅に着き、ここで昼飯。
「乾杯!」
まだスタート前なのにロング缶がテーブルに並ぶ。
゛登らずの奥寺゛はここで甲府から一緒に来た森村由梨絵とラーメンを食べて松本へ戻る。
寺ちゃんが本格的に山に参入するのはこれから数年の歳月を必要とする。
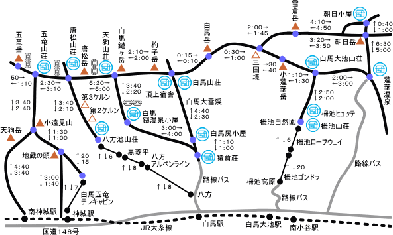
午後1時半にやっと栂池山荘を出発。
天狗原までの登り高度差350メートルは運動不足と寝不足の福井さん夫婦にはつらい。隊長はなにげなく全員に声をかけ顔色と体調を見極めている。
登り始めは常にゆっくりとしたペースだが今回はいつも以上に落とす。
戸部厚だけがマイペースで先を行く。尾瀬・燧ケ岳を登った翌日に穂高・涸沢にベースを張るという無謀な登山をする男である。
天狗原から白馬乗鞍へは直登、ダケカンバが色づき始めている。
乗鞍の頂上付近はハイマツの平原、ついつい鼻歌が出てしまうほどの気持ちのいい散歩道だ。

ゴロゴロした岩場を下りると白馬大池が眼下に広がる。
「わぁ、きれい」
あやちゃんが歓声をあげる。
深い青の湖面が小蓮華山から下りてくる風に静かに揺れている。
陽が沈みかけたしじまの黄昏の中、小屋の前にはN大学ワンゲル部のパーティ数人が場違いなウクレレの音を奏でている。
テントは二十余張り、赤、青、黄とにぎやかな彩りをみせる。
「そこが女性軍、ここが宴会場」
手際よく隊長が幕営の段取りを指示。
楽しい夕餉の始まりである。今夜のメインはレトルトの牛丼、酒のつまみは刺身の盛り合わせともいかずサンマ缶、サバ缶、ヤキトリ缶と缶詰づくし、十数缶が並ぶ。
酔うほどに声も大きくなり、笑い声が静かなテント場に響き渡る。
「もう少し静かにして下さい」
三軒隣のテントから、毎度おなじみのイエローカードだ。
下界ののん兵衛が山に入ったからといって禁酒できるわけもない。
8時就寝が望峰倶楽部山岳会の鉄のおきてだが守られたためしがない。
「さて休むか」
隊長の腕時計はすでに午後10時を回っている。
福井さんのいびきがその夜、南小谷の駅まで聞こえたらしい。
5時半に目が覚めた。周りのテントからはヘッドランプが点り始めている。
(どうしてうちのパーティは皆、朝寝坊なんだ)
隊長が寝付きがいいだけである。普段の生活のリズムから急に山のリズムには入れない。隊長はシュラフにもぐり込んで10秒と起きていられない。
「隊長の鼾は最初の10分だけ、あとは静かよ」
ゆかりちゃんは山ではいつも夜中まで眠れず、いつの間にかそれぞれの部員の鼾のくせを聞き分ける能力を身につけていた。
「おはよう」
「おはようございます」
北川、あやちゃん、やかりちゃん、そして福井さん夫婦が起きだしてきた。
戸部厚だけがテントの中に入る朝日を顔面に受けながらまだ寝息を立てている。
昨夜は寝不足だった福井さんも、すっかり元気を回復している。初参加の福井さんの奥さんも山の雰囲気に慣れたのか、昨日はあまり見られなかった笑顔がこぼれている。
周りのテントはほとんどが撤収されている。いつもながらこの山岳会は朝がゆっくりだ。下界と同じ時間帯で動いている。
隊長の導入教育の誤りである。このままほっておくと、
「10時にお茶してから登りましょ」
なんて言いかねない。
8時出発で決定。
「今日は白馬のピストンだから、手ぶらでいいわね」
あやちゃんがふとつぶやいた。
「手ぶらは隊長だけ、隊員はザックを背負う」
「あらっ、昨日のザック、一番軽かったのは誰だったかしら」
栂池ロープウェイでザック持込料金を取られなかったのは隊長だけ、10キロ以下の女性軍より軽いザックを一日、背負っていたことになる。
「隊長は常に最悪の事態を想定して体力を残しておかなければならないのだ」
みんなの視線が冷たい。
「それではカメラを持つことにする」
隊長は北川の首にかかっていたニコンを取り上げ自分の首にかけた。
テント場の境界線を示す石をまたいで一歩踏み出そうとした瞬間、帽子を目深にかぶり髪を肩まで伸ばした女性が隊長たちのパーティの前をすり抜けていった。
「あっ、あぶない」
「キャー」
石につまづいた隊長の体がザックごと女性のお尻めがけて突っ込んでいった。
「申し訳ない」
倒れた隊長が見上げた足元に赤いストッキング。
「あなたは!」
「貴女は那須の遭難碑の―――」
なんという偶然、なんという出会い。
北川が大きく口を開けたままだ。
あやちゃん、ゆかりちゃんもあまりの偶然にしばし唖然としている。
「しかし、まさかこんなところで会うとはー」
隊長の目がきらきら輝いている。
「ええ、驚きましたわ、白馬でまた会えるなんて」
玲子は加藤をリーダーとする五人のパーティで来ていた。
「じゃあ、昨夜はここのテント場でしたか」
「そうです。ゆつくり休めましたわ」
キャンプファイアーでもやって騒げば一緒に飲めたかも知れない。馬鹿なことを考える隊長である。
「我々は白馬を往復して今夜もここに泊まります。貴女方は?」
「私たちは今夜は頂上宿舎のキャンプ場です」
「我々もそうしよう」
と言いかけたが安易な計画の変更はさすがの隊長でも出来ない。
「頂上まで一緒ですね」
北川も嬉しそうだ。
それぞれメンバーを紹介しあって出発。
玲子のパーティは5名、リーダーの加藤、50代の大森、玲子より四つ年上の真弓、そして昨年に入社したばかりの吉沢。
加藤以外はC証券の社員である。F電機のパソコンの取り扱いでC証券に出入りする加藤はいつの間にかC証券の山好きな社員と酒を酌み交わす仲間になっていた。
白馬に登りませんかと、加藤に言われた時、玲子はある思いが胸に広がっていき、
「ぜひ連れていって」
と即座に加藤に返事をした。
小蓮華岳の山頂でパーティ全員が並び記念撮影。三国境の道標から雪倉岳へと続く登山道が見えてきた。
「頂上まであと、どれくらい」
あやちゃんは昨夜、睡眠不足らしく足を止めるたびに大きくあくびをしている。
「あそこから1時間だ」
三国境を指差して隊長が元気づける。
南斜面にスパッと切れ落ちた稜線の彼方に白馬の街が見える。

11時40分、頂上着。
唐松、五竜のどっしりとした山容が北アルプスらしさを映し出している。
「ここで昼飯にしよう」
福井さんが珍しく自分の意見を言った。
「すぐ下に小屋があります。そこで食べましょう」
隊長に簡単に覆された。
1,500人収容の白馬山荘もこの時期は大半の棟を閉めている。
100メートルほど下の村営頂上宿舎を見下ろすベンチに腰を下ろしランチタイムとなる。
「北川君、乾杯のビールを」
「了解しました」
北川が売店に飛んで行き暇を持て余している小屋の従業員に大声で言った。
「ロング缶10本」
「それが、ビールが切れてましてーー」
「たわけ!もう一度在庫確認しいや」
あまりの剣幕に驚いた従業員、裏の倉庫にすっ飛んでいった。
「ありました」
「そうやろ、よく探せば出てくるもんや、1本まけとけ」
そうはいかない。
「それでは乾杯」
「カンパーイ」
12人の宴会になってしまった。
「明日の予定は」
「雪渓を下って帰ります」
加藤がビールを飲み干して言った。
「我々も明日は下山です。またどこかの山で会いましょう」
隊長も山専用の大ジョッキを飲み干してご機嫌である。
ビールの追加に何度も売店往復している北川が従業員と友達になったらしい。
「これ頂いてきました」
スナック菓子とワンカップを数本持ってきた。
「あまり飲みすぎないでね、北川さん」
ゆかりちゃんがまた、心配している。
「あとは下るだけや、ねえ隊長」
「そう、下るだけ」
隊長と北川の飲みっぷりに福井さんの奥さんがあきれ返っている。
2時に二つのパーティは分かれた。
白馬大池のベースに戻る隊長たちのパーティは小蓮華で一本立て、あやちゃんがマリにケイタイを入れる。
「マリちゃん、私たちいま小蓮華岳の頂上なの」
「あたし、これからパーティ、おばあちゃんのー」
「ここで、ばあちゃんの米寿の万歳をしてあげる」
隊長はお年よりにも優しい。
マリのおばあちゃんは誕生日が10月10日、毎年この秋の山行にぶつかりマリは欠席となる。しかし下山後の松本での打ち上げの宴会には必ず出席する。

白馬大池、二日目の夜
満天の星が頂上に降りそそぎ
漆黒の山塊に囲まれた孤独な山の旅人たちは
吹き抜けていく風の音に心やすらぎ
こずえのささやきに神々のシンフォニーを聴く
しずかに、しずかに、遠き嶺の夜はふけていった
翌朝、玲子はただならぬテントの外の気配で目をさました。
「すぐに警察に電話してくれ」
加藤のあわてふためいた声が聞こえてきた。
玲子はテントのファスナーを開け、あたりを見回した。
従業員らしい男が小屋の中に走って行くのが見え、騒ぎで小屋から数人の宿泊客が出て来た。
「人が死んでいるらしい」
「警察に連絡している」
すでに出発の準備をした小屋泊まりの客が玲子たちのテントに近づき話しているのが聞こえる。玲子は震える足を登山靴に入れ、二,三歩、歩き出した。
そこに加藤が立っていた。玲子を見て、
「大森さんが死んでいる」
吐くように言った。
一人用のテントの中で玲子の上司・大森充が胸と首を刺され、テントを血の海にして死んでいた。
北川が珍しく隊長より早く起き出してコーヒーを沸かしている。
「おっ、早いね」
隊長も起き出してきた。
「昨夜は眠れたかい」
「ええ、ぐっすり」
「俺のいびきは?」
「いえ、熟睡してましたからわかりません。コーヒーをどうぞ」
「ありがとう」
皆、起き出してきて全員で夜明けのコーヒーん白馬頂上宿舎のテント場で起きた事件など知るよしもない。
朝食を済ませ今日はいよいよ下山である。
隊長はザックのパッキングを終えテントを張った跡地を塵ひとつ無い事を確認してからザングツの紐を締めるのが習慣になっている。
今日一日の行動の安全を祈るかのようにしっかりと、そして入念に結ぶ。
そんな隊長の姿をなにげなく見ていたあやちゃんには紐を結んでいる隊長の右の登山靴に赤黒いシミが見えたような気がした。
「さあ、出発だ」
隊長の掛け声にかき消され、すぐにそんな思いは薄れていった。
第5章 カクテルの甘いささやき へ
|
|
|
|