|
第9章 星明りの裸身
|
|
「ねえ、信次郎さん、お彼岸はどうするの?」
北川の耳がピクリと動いた。
「信州へ帰ろうか」
「そうね、わたしも、お腹が少し重くなってきたし」
北川の妻は二人目の子を宿していた。
二月の異動で北川はK製薬小田原工場の品質管理課長に昇進した。三十代前半の異例の抜擢である。
(女房の実家にも課長になった報告をして、少しは自慢せな――、それに久しぶりに山にも登りたいし)

涸沢のナナカマド
去年の秋の白馬から帰ったままの彼の登山靴は泥がついたまま物置にしまいこまれていた。
(3月の半ばか、どの山がいいんやろ、そうや隊長に電話しよ)
一瞬ためらった北川は、意を決して隊長の家に電話をかけた。
「はい、香山です」
「たっ、隊、いや、ご主人いらっしゃいきすか、香山さん」
「いいえ、主人は海外に出ております」
「海外ですか?」
「はい、なんでも香港に買い物に行くとか――」
「買い物ですか」
「北川さん、お元気?」
「はっ、はい、なんとか」
「主人は、最近、家に寄りつきませんの、北川さんと山にでも、こもってるのかと思ってましたわ」
「い、いえ、私は仕事が忙しくて、とても山なんか――、いっ、行ってられません」
「そう、それは結構ですこと」
「しっ、失礼します」
冷や汗が出た。
(なんやねん、香港に買い物やて)
北川はあの隊長のスケベそうな茶のメガネを思い浮かべた。
(また玲子はんとデートかいな、しょうもない)
せっかくの信州行きである。しかし北川には三月の北アルプスをイメージするだけの山の経験がない。
(そうや、奥寺さんに聞いてみよか)
「もしもし、奥寺さんのお宅ですか」
「はい、そうですが」
「北川ですが、ご主人いてはりますか?」
「主人は出ております。なんでもロスに出張だとか」
「ロッ、ロスアンジェルスですか?」
「はい、2週間ほど、行ってくるとか」
「しっ、失礼します」
(なんやねん、香港とか、ロスとか、ええかげんにせい)
更埴のあんずの里、まだ早い春、花はつぼみ。
「わいなぁ、山に行ってくるやん」
出店の焼き鳥屋だけは忙しかった。
ワンカップを二杯引っ掛けたあと、北川は妻に言った。
「気ぃつけてや」
とは言わない。妻の博子はここ信州、更埴の生まれ。
「ほな留守頼むで――」
「まかしときぃ」
とも言わない。
ワンカップをもう一杯、干してから、ケイタイで松本支部の女性軍にかけまくった。
あやちゃんは、横浜教育センターへ来期計画会議出張。
ゆかりちゃんは、業務部打ち合わせで大阪本部出張。
マリちゃんは新薬セミナーのドイツからの講師お出迎えで成田出張。
急にさびしくなった。
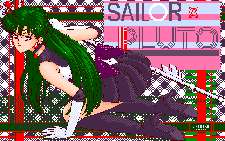
諏訪営業所のころを思い出した。
「そうや!早苗ちゃんや」
4年前、笠原早苗は北川の部下だった。
日本人形のような涼やかな目元をした早苗は、そのしぐさまでが京都的だった。
「もしもし、早苗ちゃん、北川です。お久しぶり」
「わっ、北川さん、しばらくです。元気でやってますか」
「うん、私用で信州に来たから、なんとなく君の声が聞きたくなって―」
「会いたいわ」
胸が熱くなった。
「山に一緒に行かへん?」
早苗は幼いころから、からだが弱く、地元の高校を卒業してK製薬松本支店に入社してからも、通院を繰り返していた。
「ねえ、早苗、今度スキーに行かない?」
同僚たちから誘われても、早苗は首を横に振った。父から厳しく言われている。
「おまえは生まれつき体が弱い。みんなと同じようには動けないんだからスキーなど行かずに家でおとなしくしてなさい」
一人娘の早苗はいつも両親と夕食を共にした。
仕事柄、帰りはいつも8時近くになる。父は早苗が帰ってくるまで夕食のはしをつけることはなく、家族3人がそろって、初めてビールを口にした。
「上高地まで歩こうと思ってるんや」
「えっ、上高地!」
早苗の家は塩尻、この時期の上高地がどんな所かは少しは検討がつく。
「心配いらへん、中年のおばはんなんかが、けっこう歩いてるんや」
本で読んだ知識を披露した。
――ハイキングなんか中学生の頃、父に連れられて行った[高ボッチ]以来だわ――。
「行こうかな」
北川が山に登ることは彼の口から時々、聞かされていた。
――北川さんとなら安心かも――。
「じゃあ、明日の朝、迎えに行く」
翌朝6時、早苗は洗馬小学校の前の電話ボックスの横で北川を待った。3分後に北川の車がライトを点灯させたまま静かに早苗の前に止まった。
「こんな格好でいいの?」
早苗は体を反転させながら、北川に聞いた。
靴はキャラバンシューズだが、とりあえず冬山の支度になっている。パステルピンクのダウンジャケットが早苗の顔をひときわ白くさせていた。北川は迎えの車の中、早苗の姿を想像しながら運転してきたが、思ったとおりの装いに、また胸が熱くなった。
「充分や、あとはわいの装備でなんとかなる」
独身の女性と二人きりのドライブなんて何年ぶりだろう。北川はいつもの山に登る前の気分の高揚とは違った胸の高鳴りに幸せでいっぱいになった。
逆巻温泉の駐車場に車を止め、歩き出す。
[冬季通行止め]の標識が158号線をふさぐゲートの横に立ち、数台のRV車が雪をかぶったまま駐車してある。車のナンバーを見て早苗が言った。
「みんな遠くから来てるのね」
「地元のひとはあまり来んやろ」
「私だって上高地なんて高校を卒業した時に友達と一度来たきりだわ」
朝日が梓川の川面をキラキラ輝かせている。
北川は楽しくなってきた。
30分で安房峠との分岐、中ノ湯温泉から立ち上がる白い煙が山肌についた雪と混ざり合う。
少し体が汗ばんできたころ、釜トンネルの入り口に着いた。

「中は真っ暗や」
裸電球が天井の岩盤から20メートルおきにふら下がっている。
「そうそう、これ」
北川がヘッドランプをザックから取り出し早苗の頭に乗せた。
「気ぃつけて歩こう」
と言った瞬間、北川が転倒した、というより滑った。
「あ痛、たっ」
「大丈夫、北川さん」
尻と右ひじを思いきり岩にぶつけた。倒れたままずれたヘッドランプを直し、灯りの照らす方向を見た。
「ありゃ、凍ってる」
この時期の釜トンネル、あなどれない。氷と岩の回廊、しかも登り斜面である。
「気をつけないと危ないわ」
二人は手をつないで慎重に歩き出した。
水滴のたれる音だけがトンネル内に響き、左に少しカーブしたところから傾斜がきつくなってくる。
回廊の中央部はほとんど、おうとつのない氷の板、ヘッドランプを左右に振ると、右側の壁にはところどころ岩が氷の上に頭を突き出している。
「そっちのほうが安全だ」
ゆっくりと早苗の手を取り、岩の上に足を乗せ次の岩を選びながら歩く。
何度もバランスをくずし転倒しそうになる。
「怖いわ、わたし」
北川が早苗の手を強く握りしめ離さない。
「ゆっくり歩けば大丈夫や」
早苗は足が前に出なくなった。
「そうや、アイゼンがあった」
ザックの中に買ったばかりのアイゼンを入れてきたことにやっと気づいた。
「これさえあれば百人力や」
でもアイゼンは一足。
「半分こ、しよか」
右の靴にぞれぞれアイゼンを装着し、妙なバランスで二人はやっとトンネル出口にたどり着いた。
「うふっ、おかしかったわ、北川さんの歩き方」
「なんや、君だって、右足と右腕が一緒に動いてたやんか」
何年ぶりかで会った恋人どうしのように二人は手をとりあって笑った。
「夏は、このトンネルをタクシーに乗って通過するだけだったから、涼しくていいなと思っていたけど、冬の表情ってこんなに変わってしまうんやな」

冬の大正池
冬の上高地お散歩は隊長の恒例行事だった。
三十半ばからの八年間、毎年このコースを一人で歩いた。
「隊長は、お散歩だなんて言ってたけど、とんでもない難所やな」
北川はあらためて隊長の登山家としてのレベルの高さをかいまみた思いだった。
雪のついた焼岳を左手に見ながら、二度目の大きな右カーブを回り込むと、穂高の吊尾根を後ろに抱えた大正池が視界に飛び込んでくる。
「うわっ、きれいや」
「すごい景色だわ」
穂高連峰と大正池の二点セットの組み合わせは国内の山岳点景の中では秀逸の作品である。晩秋の日光・男体山と中禅寺湖のセットもいいが、冬から早春の出来栄えはこの穂高に尽きる。神は岳人になんと多くの芸術作品を提供してくれるのだろう。
この時期の穂高は開演を待つオーケストラの張り詰めた静けさに似ている。
曲はワグナーがいい、ワグネリアンたちの最高の楽しみは、タクトが振り下ろされる前の一瞬なのである。
カメラを取り出すのも忘れて、二人は穂高の奏でるシンフォニーを体が冷えるまで聴いていた。
「さあ、そろそろ出発しないと」
時計の針は11時を回っていた。
体が温まったころに雪をかぶった木々の中から赤い屋根が見えてきた。
「ちょっとコーヒーでも飲んでこか」
と北川のジョーク。
帝国ホテル正面玄関にはまだ背丈ほどの吹き溜まりがある。
正午をずいぶん回ったころに河童橋に到着、絵描きが軍手の先を切って筆先を動かしている。
岳沢から、単独行のスキーヤ―が降りてきた。途中、転倒したのかザックに雪を乗せていた。
西糸屋の前で昼飯、北川がウイスキーをザックから取り出すとカルガモが寄ってきた。
「早苗ちゃんも飲もか」
「うん、少しだけ」
お湯を沸かすストーブの音だけが上高地の静寂の中に溶け込んでいく。
ラーメンをつまみにお湯割りウイスキーを、北川が四杯、早苗ちゃんも二杯、体が芯から温まる。
「もうこんな時間や、そろそろ出発しよか」
「わたし、まだここにいたいわ」
早苗が北川を見つめた。
「だめや、家に帰れなくなってしまうやろ」
一瞬、北川は早苗を抱きしめたくなるほどいとおしく感じたが、その思いを振り切るように小さなザックを早苗の背に乗せた。
梓川左岸をウエストン碑に向かって歩き出す。清水屋ホテルを過ぎ、西穂への登山口を右に見て橋を渡った。
スキーの跡が梓川沿いに続いている。
「ここを下って行けば大正池や」
快適な梓川べりの雪上散歩、割谷山の稜線に太陽が沈みはじめている。
梓川が左に大きくくねりだすあたり、スキーの跡がいつの間にか消えている。
「大丈夫なの?」
「心配おまへん」
北川はスキーの指導員の資格を持っている。戸隠で2年前に取った。
雪には自信がある。
しかし、ズブッと、膝までもぐった。
「向こう側に渡ろう」
一番浅い場所を捜したが膝まではありそうに見えた。
渡って左岸に出れば大正池の西岸、平らなところを歩ける。
北川は早苗の手を取り、川を渡り出した。膝までかなと思っていた深さは太ももまであった。流れはさほど速くないが、冷たさは恐怖感を増幅させている。
岸辺までたどり着いたが、上がれない。雪屁状のオーバーハングになっている。
腰までつかって川を下降したが岸に上がれそうな個所はなかった。
(戻るしかないな)
早苗はもはや放心状態になっている。
「引き返すよ」
北川は出来る限りやさしい言葉で彼女に声をかけた。
早苗に反応はない。ただ北川の手をしびれるくらい強く握っていた。
冷たさで下半身の感覚がなくなるころ、やっと反対側の岸にたどり着いた。
陽はすでにない。
肩で息をしながら二人は太ももまで雪にもぐり、分速5メートルほどのスピードで歩いている。
早苗の体力は限界まで達している。
「わたし、もうだめ」
霞沢岳から落ちる急峻な木立が永遠にとどかない夜空の星の瞬きのように思えた。
北川が這いつくばって進み始めた。
「これって匍匐(ほふく)前進ていうの?」
難しい言葉を知ってる娘だなと妙に北川は感心した。
(こんな姿、妻には見せられないな)
おかしくて涙が出てきそう。
早苗は上下に動く北川の尻を後ろから見て思わず吹き出した。
雪面を這うこと四十分、やっと、やっと大正池右岸の遊歩道にたどり着いた。
「生きて帰れる!」
北川の叫びが、春まだ遠い穂高連峰にこだました。
深い闇が谷を覆いはじめたころ、二人は逆巻温泉に着いた。
「風呂に入っていこか」
「うん」
早苗は素直に首を縦に振った。
三百円の入湯料を払い、ぐちゅぐちゅになった登山靴を脱ぐ。
ほの暗いランプに照らされた露天の風呂には誰もいない。
星明かりの中、早苗の白い裸身だけが、いつまでも残像として北川のまぶたに残った。
第10章 雪渓の謎 へつづく
|
|
|
|