|
第10章 雪渓の謎
 朝日岳から望む隠居倉 朝日岳から望む隠居倉 |
|
|
|
茶臼からの噴煙が北にゆっくり流れている。
剣ガ峰を越え吹き上がる風はまだ冷たく、青すぎる空に会津の山々の残雪が映える。
風が玲子の髪を舞い上がらせている。
「あの山は?」
「平ヵ岳」
「あれは?」
「会津駒」
「そのむこうは?」
玲子はひとつひとつの山を指差しながら、隊長のガイドを楽しんでいる。
「あれは会津朝日、そのふもとに奥只見湖がある」
「尾瀬の山は?」
「ここからは見えない。これから行く三本槍から一望できる」
五月の連休に那須に行きたいと玲子は言った。
彼女は元恋人・中原のことを思い出したくなかったが、那須の山を話すときの俊介の熱い口調はいつも玲子を心地よくさせた。
「小屋は満員だよ」
「いいわ、布団を頭からかぶって寝るわ」
「いびきはうるさいし」
「もう慣れてる」
「消灯は早いし」
「夢をいっしょに見ましょう」
「さあ、出発だ」
二人はにぎわい出してきた朝日岳の山頂をあとにした。
熊見曽根との分岐から清水平へのなだらかな稜線は那須連山の中でも屈指のお散歩コースだ。
ハイマツ帯を過ぎ、まだつぼみを閉じたままのシャクナゲ通りを抜けると清水平(第1章参照)となる。
中の大倉尾根の南斜面にはまだ残雪が広がっている。
「面白い遊びを教えてあげる」
「えっ、なに?」
隊長はザックの中から黄色いポンチョを取り出した。
「これでスーパ―マンになるんだ」
「スーパーマン?」
「そう、空を飛ぶんだ」
「空を?」
「雪の上を!」
雪渓の上にポンチョを広げ、隊長は大の字に倒れた。
「さあ、行くぞ!」
二,三歩、足で勢いをつけると隊長はスーパーマンになった。
幅50メートル、長さ200メートルはある雪渓を黄色いポンチョが小気味よく滑走していく。
「うふっ、あのひとったら、いつまでも子供ね」
「おーい、ここまでおいで」
はるか雪渓の下まで滑り降りた隊長の声が風に乗って吹きあがってくる。
「あなた、早く戻ってきて!」
玲子が手を振りながら笑って応える。
(何年ぶりかしら、こんなに大きな声を出したのは)
「今度は君の番だ」
息を切らしながら雪渓を登ってきた隊長が言った。
「えっ、わたし!」
「すごく気持ちいいよ」
「ちょっと怖いわ」
「大丈夫さ、しっかり両手でポンチョを握るんだ。うまくバランスをとればターンも出来る」
玲子がポンチョの上に乗った。
「そらっ、出発!」
隊長が玲子のおしりを軽くたたいた。
「キャッ!」
雪渓の上を玲子が軽やかに滑り出した。
「だんだんスピードが出てくるぞ」
隊長が大声で言った。
「すごい!ほんとにスーパーマンみたいだわ」
隊長は無邪気にはしゃぎながら滑り降りる玲子を笑いながら見ていた。
「まだ子供だな」
煙草に火をつけようとしたその時、玲子の乗ったポンチョが大きく右にターンしていくのが見えた。
(あの娘、なかなかやるな)
隊長は玲子の運動神経の良さに感心した。
(スキーはそんなにうまくなかったのにな)
煙草の煙が空に舞い上がったその時、キャーという玲子の悲鳴が風に乗って下から聞こえてきた。
(おい、ちょっとおかしいぞ)
玲子の体は右に大きくターンしたまま直進し加速をつけはじめている。
「おい、左に曲がれ!」
隊長が大声でさけんだ。
「左に曲がるんだ。あぶない!」
「助けて!あなた」
玲子の声が小さく聞こえ、真っ白い雪渓の上を黄色いかたまりは斜行し、そして突然消えた。
潅木帯に突っ込んだのである。
煙草をほおり投げ隊長は雪渓を駆け下りた。途中つまづいて転倒し5、6メートル転がり落ちた。
「いたた」
顔面に雪がついた。
「玲子!」
声になってない。
雪渓下部の右側に着いた。
「玲子!」
大声でどなりながら潅木のしげみに入った。
その瞬間、隊長の心臓が止まった。
がけである。
幅10メートルくらいにわたって毘沙門沢の方角にスパッときれ落ちている。
(こんながけがあったなんて――)
潅木につかまり下をのぞきこんだ。
がけ下まで5メートルはある。
「おーい、玲子、大丈夫か!」
のぞきこんだまま隊長は何度も叫んだ。
「今すぐ降りていくぞ」
潅木につかまりながら、尾根の南斜面のハイマツをボキボキと音をたてて折りながらがけの下にたどりついた。
「玲子、どこにいるんだ」
左右を見回すが、いない。
「返事をしろ、玲子」
がけ下のガレがそのまま沢に落ち込む地形になっている。
「玲子――」
谷に隊長の声がこだました。
谷すじにそって降りてみる。
ところどころに雪をつけた石があるが人が落ちたような形跡はなかった。
(こんなところまで落ちるはずはない)
落ちたあたりまで戻り上部を見上げた。
潅木帯を突き抜けた時に一緒になって落ちた雪が岩についている。がけを右手からまわり込み落ちた雪渓のはしに戻り、再び下をのぞきこんだ。
(どこにいったんだ)
鳥の声がやむとあたりはとたんに静かになる。
(こんな事ってあるか)
ポンチョも見当たらない。
(もしかして上に戻っているのか)
彼女はいたずら好きだ。きっと滑り降りた元の場所に戻っていて驚かすつもりだ。
息を切らせながら雪渓の上まで登りついた。
さっきのままだ。
赤と青のペアのザックが開けられたまま置いてある。
隊長はザックの上に座り込みポンチョのつけたトレールをゆつくりと目で追った。
すでに玲子がいなくなってから1時間がたっていた。
(夢か――)
手についた雪が冷たい。
(夢じゃない)
三本槍側からガスが吹き上がり、歩きまわった隊長の背中の汗を氷のように冷やした。
もう一度、雪渓を降りはじめる。つい1時間前の彼女の足跡をたどって――。
がけの上部、下のガレ場、さして沢すじを丹念に捜したがどこにも人の落ちた形跡などなかった。
まだ陽は高い。
(助けを呼ぶか――)
朝日岳付近まで戻れば、登山者がいるはずである。
ケイタイで下に連絡をとれば、すぐ事情を聴き捜索隊が組織されるかも知れない。
隊長の頭の中で砂あらしが巻き起こった。
ゴーゴーとうなりをたて、男を孤独の淵に追いやった。
しばらくして、その嵐がやんだ。
砂漠とも雪渓ともつかない白い斜面に男は立ち上がり、赤いザックを取り上げ雪渓を下り出した。
玲子が落ちた場所まで来たその時、男はザックから身元がわかりそうなものを抜き取り、力いっぱい空に向かって放り投げた。
――さようなら、玲子――
峰の茶屋の避難小屋は登山者であふれていた。
つい数時間前におこった事故がうそのようだ。
隊長は小屋から十メートルほど離れ岩に腰掛けた。
茶臼の噴煙をバックに写真を撮る者、水筒をうまそうに口にふくむ者、いつも見かけるゴールデンウィークの山の光景である。
岩に静かに腰掛ける隊長を見て、だれもが疲れた中年の登山者と思うくらいだ。
しかしその中年男の心は動揺していた。
(発見されなければ――)
すでに時計の針は午後四時を回っている。
この時間から清水平に向かう登山者がいるか、隊長はそれだけが気がかりだった。
山の行程からいけば、この時間から朝日岳、清水平に向かう登山者などいない。
一時間ほど小屋から動き出す者を注意深く見ていたが、茶臼岳方面から下りてきてロープウェイ山麓駅へ戻る登山者が大半であった。
朝日岳方面から下りてくる者も数人いたが隊長とは時間差があった。
(清水平付近での俺の姿は見られていない)
太陽が茶臼の稜線に沈みかけていた。
最後の登山者が小屋を後にしたのを確認し、隊長は下り始めた。
広いガレ場にはいくつもの小さいケルンが積んである。
立ち止まった隊長は振り向き、アルペン的風貌を持つ朝日岳を見上げた。
――さようなら、玲子―――。
山を下りて四日目の朝、隊長は地元紙の社会面に小さな記事を見つけた。
[宇都宮の女性、那須で行方不明]
「五月三日、単独で那須岳に登った宇都宮市南宿郷の風間玲子さん(24)が下山予定の四日夜になっても戻らず、父親から黒磯警察署に連絡があった。五日、地元消防団と那須山岳救助隊が捜索に向かったが手がかりはつかめていない」
見逃してしまいそうな小さな記事だった。
(そうさ、山での遭難など、毎年何百件もある。女性の単独行者の事故だって年々増えている。このまま行方不明で終わるな)
隊長はほっと肩をなでおろし、コーヒーをすすりながら自分に言い聞かせた。
――あれは事故だった。
あの後、何時間も俺は彼女を捜した。
その時、岩にぶつけた傷や、木にこすった傷もある。
彼女を一生懸命捜した。
もうどこにも見つからないはずだ。
永遠に風間玲子は行方不明のままだ。
父親は警察や捜索隊と連絡を取り合って、とうぶん捜索を続けるだろう。
しかし、あの場所は登山道から数百メートル離れている。
女性が単独で入り込むところではない。
残雪が解ければ、来年までは人が来る可能性はゼロだ。
玲子が見つかってほしくない。
俺にも家族がある。
女房はともかく子供にだけは知られたくない。
事業も順調に伸びている。
こんなところでつまづいたら俺の明日はなくなってしまう。
那須山岳救助隊は三日間、捜索を続けた。
「あの時もそうだったな」
那須の遭難を手がけて二十年になる岡田がぽつりと言った。
「十四年前のあの事件か」
「そうだ、S大ワンゲル部の遭難だ」(第1章参照)
「もう十四年も経つんだな」
黒磯署の富永が感慨深げにつぶやいた。
「この那須にオロクさんが何人いるのやら」
「鏡沼のホトケさんもまだ上がってなかんべ」
富永が口惜しそうに、茶臼からわき上がる煙を見上げた。
「玲子は一人で登ることが多かったようです」
黒磯署の応接室で白髪が混じりはじめた玲子の父親は語り始めた。
「数年前に婚約者を山で亡くしまして、それ以来あの子は一人で山に登るようになりました」
「ほう、かわいそうな事をしたな」
「山なんて登る子じゃなかったのに――」
中原への恨みが玲子の父の心にしみ込んでいる。
「お父さん、玲子さんのその後は?」
「その後?」
「好きな男性が出来たとか――」
「いや、あの子はそんなことはありません」
きっぱりと言い切った。
富永は煙草に火をつけながら窓の外をながめた。
(捜索は打ち切りだっぺ)
五日間の捜索でなんの手がかりもつかめなかった。
遭難者の身につけていたもの、登山道での情報、下山口の目撃者、なにひとつ玲子に結びつくものはなかった。
十日ほどたったある日、一本の電話が黒磯署にかかった。
「えっ、三日に若い女性の登山者を見た!」
「はい、ぼくは前日、三斗小屋に泊まり大峠から三本槍をやって朝日岳に登りました」
「どこで遭った?」
「隠居倉への分岐あたりです」
「間違いねぇか」
「ええ、あの新聞の写真にそっくりでした。でももう一人の男性はあまりよく憶えてません」
「なに!もう一人の男性だと――」
「ひげをはやしていたのは憶えています」
「ひっ、ひげの男だと!」
東京の大学に通う鈴木は連休を利用して地元の那須に登った。
五月の半ばに帰省し母から遭難者のことを聞いたのだ。
黒磯署に呼ばれた鈴木は玲子とすれ違った時の状況を富永に話し始めた。
「三日の午前10時くらいだと思います。三斗小屋を出たのが7時でしたから」
「隠居倉の分岐あたりでか?」
「そうです。道標を見て正面の朝日まであと20分くらいだなと、思いました」
「一緒にいた男のことをもう少し詳しくきかしてくれや」
「年齢はたぶん四十代だと思います。いや、もう少しいってるかもしれません」
「どんな男だった?」
「ひげ面でしたけど、知的な感じのする――、そう、ポール・ニューマンみたいな」
「なに!ポール・ニューマンだと、あの[明日に向かって撃て]のポール・ニューマンか?」
「ぼくは[大脱走]と[栄光のルマン]しか見てません」
「けっこう古いの見てんな」
「車が好きなもんで」
「だけんど[大脱走]と[ルマン]はスティーブ・マックィーンだっぺ」
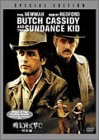 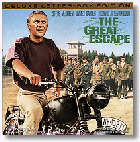 
富永が調書を取るボールペンをせわしなくいじり出した。
(振り出しに戻りだっぺ)
玲子の捜索は山岳救助隊の手を離れ、黒磯警察署及び栃木県警の管轄に置かれた。
「ひげのポール・ニューマンか――、やっかいな事になったんぺ」
富永警部が頭をかきながら、つぶやいた」
第11章 北の国からの電話 へつづく
|
|
|
|