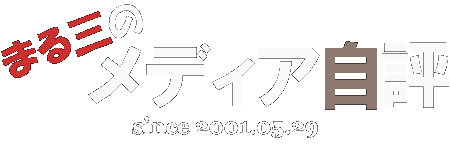2003.8.2
たとえば大相撲の行司は「時間いっぱい、待ったなし」とは言うけれども、立つタイミングは両力士に任されている。合わなかった場合には「まだまだまだ」と言って止め、合った場合には「はっけよい 残った残ぉった」と続ける。
いっぽう(アマチュアの)相撲大会の行司は「はっけよい……残ったッ」と掛け声をかけながら両選手の前にかざしていた手を引っ込め、立つきっかけを与える。以前はアマチュアの大会でも両選手に立つタイミングが任されていたそうだが、外国人選手から「解りづらい」と苦情が出たため変更したらしい。
たとえば柔道の国内大会では、組んでからの技の掛け合いが大きな比重を占める。
いっぽう国際大会では、組み手争いが大きな比重を占める。
さらに柔道の国内大会では、寝技の態勢になっても「待てッ」となるまでの時間はかなりある。
いっぽう国際大会では、両選手が倒れたらあっという間に「待てッ」だ。国際大会に出場する選手は(日本人選手も含めて?)寝技は得意としていないようで、膠着状態に陥ってしまうことは確か。
ここらへんが日本の“××道”における“国際化”かもしれない。つまりは、競技(勝ち負け)は輸出できても精神を輸出するのは難しい、ということだ。
毎年11月3日文化の日に「剣道全日本選手権」が行われており、まる三はNHKの中継で見ている(剣道未経験者にもかかわらずなんとなく好きなのだ)。それを観ていて思ったのは――
剣道の国際化は難しいかも
ということ。一番の障害はひょっとすると“審判”じゃないかと思った。シドニー五輪の篠原vsドイエ(仏)戦を持ち出すまでもなく、“××道”の審判は難しい。特に剣道の試合は電光石火で、どちらが有効打を放ったかどうか判断するのは素人には難しく、スロービデオで観てはじめて「なるほど」と思うようなことが多い。
ここからやっと本題なのだけれども、31日深夜、NHK総合で『にんげんドキュメント ただ一撃にかける』の再放送をしていた。第12回剣道世界選手権に出場した栄花直輝 六段のお話だったのだけれども、この番組を見る限り、精神面まで含めて“××道”の国際化に成功したのが剣道かもしれない。だって、団体決勝日本×韓国の延長戦(代表戦)の決着後、栄花六段のもとに歩み寄った外国人選手が感極まって泣いてしまう光景も見られたりするのだ。
もしまる三に子供がいたら「ラグビーをやって欲しいなぁ」と思っていたけれども、「剣道もいいなぁ」と思いました。