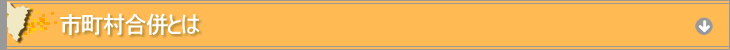|
 |
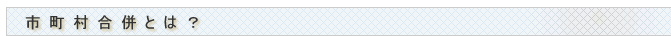 |
 |
| |
市町村合併とは、2つ以上の市町村が1つの市町村になることです。合併の方式には、新設合併と編入合併があります。新設合併とは、A町とB町が合併して、新たにC町が誕生する場合を言います。編入合併とは、A町をB町に吸収する合併を言います。
|
|
| |
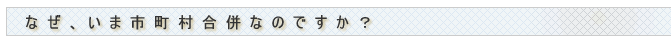 |
| |
市町村が今の形にほぼ整ったのが、昭和30年ごろの「昭和の大合併」と言われた時代であり、その後40年以上が経過しています。その間、市町村を取り巻く環境は、日常生活圏の拡大、行政ニーズの多様化・高度化、少子・高齢化の進行、厳しい財政状況等大きく変化しています。とりわけ、近年は地方分権の時代と言われ、住民に身近な市町村は、住民のニーズに応じた行政サービスを提供する上で中心的な役割を期待されています。ますます多様化・高度化する住民ニーズに対応できる行財政基盤の強化が、急務となっています。
このような課題に、市町村が的確に対応するための有効な方法の一つが「市町村合併」と言われています。
|
|
| |
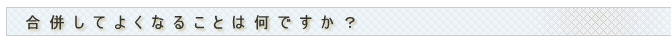 |
| |
市町村合併のメリットは、主に次のようなことがあげられます。
- 住民の利便性およびサービスの向上
現在ある各町の庁舎を支所として活用することによって、住民票などを勤務先や出かけ先の近くの窓口で取ることができたり、合併する市町村内であれば、どこでも同じ窓口サービスを受けることができるようになります。また、単独町では配置困難な専門職を採用することができ、高度なサービスの提供が可能となります。
- 行財政運営の効率化と基盤強化
これまで各町で整備されていた類似施設が、広域的観点から重複投資が解消されます。また、3役・議員・各種委員などの総数が減少することにより、人件費を削減することができます。さらに、総務や企画などの管理部門の効率化が図られることにより、サービスや事業を直接担当する部門に適正な人員を配置することによって、住民一人ひとりへの対応を充実させることができます。
- 重点的な投資による基盤整備
合併により財政基盤が強化され重点投資をすることができ、グレードの高い施設の整備や大規模なプロジェクトの実現が可能となります。
|
|
| |
 |
| |
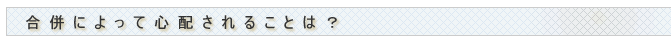 |
| |
市町村合併のデメリットは、主に次のことが考えられます。
- 役場が遠くなって、今までより不便になる。
- 中心部だけよくなって、周辺部がさびれる。
- 住民の声が届きにくくなって、サービスのきめ細かさがなくなる。
- 各地域の歴史・文化伝承などが失われる。
- 財政状況に差がある市町村合併は、財政状況のよい市町村に不利になる。
- 福祉などのサービス水準が今までと比べて低下したり、水道料金などが高くなる。
これらのデメリットについては、合併協議会で解決または最小限とするよう十分協議・検討していきます。
|
|
| |
 |
| |
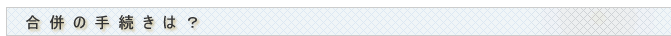 |
| |
まず合併をしようとする市町村は、合併協議会を設置します。合併協議会は、これから合併後のビジョンを描く市町村建設計画の策定や新市における多くの事務事業の調整・協議など、合併に関するあらゆる協議を行います。合併協議会で話し合われた主な項目は、合併協定書としてまとめられます。次に、合併協議会での協議結果をもとに、それぞれの市町村の議会で合併についての議決を経て、都道府県知事に合併の申請をします。その後、都道府県議会での議決、国の告示があってはじめて合併の効力が発生することとなります。
|
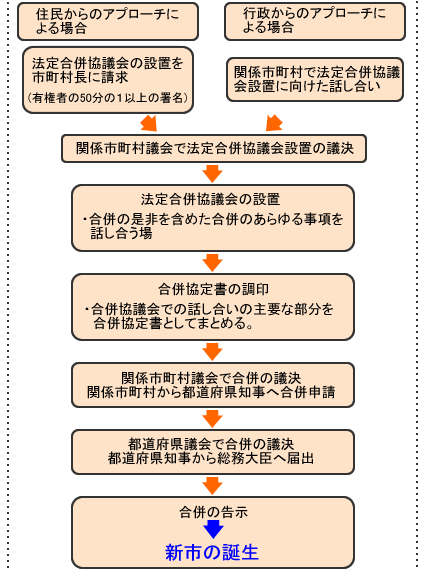 |
|
| |
|
 |
| |
|
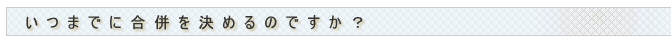 |
| |
|
合併を決める期限はありません。市町村の合併は、地方自治法による手続きを経ればいつでもできます。しかしながら、国や都道府県の財政支援などのある現在の合併特例法の特例措置は、平成17年3月31日までとなっており、支援を受けるために期限までに合併すれば、合併後のまちづくりに有利と言われています。
|
|
| |
|
 |
| |
|
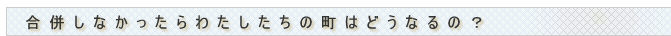 |
| |
|
3町の歳入は、国から交付される地方交付税が大きなウェイトを占めています。しかし、国では財政悪化に歯止めをかけるべく、現在、地方財政構造の改革を進めており、地方交付税については、国庫補助負担金、税財源の移譲とともに見直すこととされています。
一方、市町村では少子・高齢化の進展や地方分権による権限の移譲、環境問題や情報化など新たに対応していかなければならない課題が発生しています。
こうした状況に市町村が適切に対応していくためには、合併により市町村の人的・財政的な基盤を強化することが最も有効な方策の一つと言えます。
合併を選択しない市町村は、別な方策、例えば徹底的な経費削減や事業の選別を行うことにより、こうした厳しい状況に対応していかなければなりません。
|
|