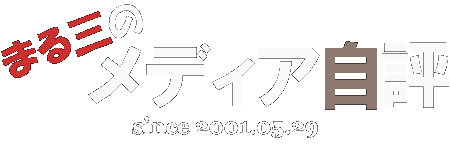2001.7.8
予告した通り、三行書評番外篇です。
三行書評と銘打ってはいるものの、あらまし3行+コメント3行を目安に書いているので実質“6行書評”だなぁなんて思い始めた今日この頃^_^;。それはちょうどヨドバシカメラのCMで、「どのくらいで届くの?」「3日!!」と両手を出して答えるので6日になってしまう女性店員みたいなものだ。ローカルな話でスミマセン。
さて本題。
最初に、お薦め度=五つ星のこころを解くと、皆さんにも評価して欲しいのだ。読んでみて「なるほどこれはためになる」なのか、「うーん困った」なのか。そういう五つ星である。
まずは以下の文章を読んで欲しい。
たとえば、新聞社では、「勧進帳」といって、時間のない場合に、メモを頼りに頭で文をまとめながら、電話で、じかに本社に送稿したりすることがあります。これを「勧進帳」と呼ぶのは、歌舞伎の『勧進帳』で、武蔵坊弁慶が、安宅の関において、白紙の巻紙を勧進帳として称して読み上げ、無事に関所を通行するという故事からでたものです。
これは、46ページから47ページにかけて載っている文章である。「読点は、少ないよりは多いほうが読みやすいことはたしか」で、「編集者のかたに『荊木さんの文章は、読点が多いですね』といわれますが、それは、むしろ、ほめことばだと思ってい」る筆者が書いた文章なので読点=テンが多い。語順はそのままで、僕の基準ではどう考えても不要と思われるテンを削ってみたのが次の文章だ。
たとえば新聞社では、「勧進帳」といって、時間のない場合にメモを頼りに頭で文をまとめながら、電話でじかに本社に送稿したりすることがあります。これを「勧進帳」と呼ぶのは、歌舞伎の『勧進帳』で、武蔵坊弁慶が、安宅の関において、白紙の巻紙を勧進帳として称して読み上げ、無事に関所を通行するという故事からでたものです。
機械的にテンを削ったのでリズムが悪く読みづらいかと思う。そこでもう一段階進めて語順にまで手を加えてテンを減らす努力をしたのが次の文章だ。
たとえば新聞社では、時間のない場合にメモを頼りに頭で文をまとめながら電話で直に本社に送稿したりすることがあり、これを「勧進帳」と呼びます。これは、歌舞伎『勧進帳』の「安宅の関の場」において、武蔵坊弁慶が白紙の巻紙を勧進帳として称して読み上げて無事に関所を通行するという故事からでたものです。
どうだろう。解かり易さが減じてしまっているだろうか?
もう一つ例を挙げよう(AおよびBは本書42〜43ページで取り上げられている)。
- 刑事は血まみれになって逃げる犯人を追跡した。
- 刑事は血まみれになって、逃げる犯人を追跡した。
- 刑事は、血まみれになって逃げる犯人を追跡した。
- 刑事は、血まみれになって、逃げる犯人を追跡した。
Aでは意味が曖昧だ。Bならば血まみれなのは刑事だ。Cならば血まみれなのは犯人だ。ところが、Dのようにテンを打つとまた曖昧になる。
つまり、「読点は、少ないよりは多いほうが読みやすい」というのは誤りだといえる。
さらにもうひとつだけおかしな点を挙げておく。「第八話 卒業論文を書く」で引用について述べて注意点をいくつか述べているが、そのなかに「出典を明記すること」がある。テンの重要性を論じる例文として挙げた「刑事は血まみれになって逃げる犯人を追跡しました」は、永野賢氏が『ことばの研究室IV・正しい表現』(日本放送協会編/1954年)で挙げている「渡辺刑事は血まみれになって逃げ出した賊を追いかけた」に酷似している(本多勝一『日本語の作文技術』(朝日文庫)による)が、出典の明記はない。「原文通りではないから」という声が聞こえてきそうだが、人の手柄を横取りするようなやり方のほうが、考えようによっては悪質だ。
本書の活字は10ポイント。普通の新書や文庫は8ポイントだから少々大きめ。全138ページだからかなり薄い。驚くなかれ、これで値段は税別1200円! 僕は図書館で借りたのだが、誰が買うのか不思議である。
| あ、見っかちゃった^_^;。著者の荊木氏は某大学の助教授だから学生に買わせるというテがある。そういう阿漕(あこぎ)な先生がたまにいる。学生がかわいそうだ。 |