小栗内外大神宮太太神楽 筑西市小栗1番地 県無形民俗文化財
神楽といえば、関東では鷲宮神社(埼玉県)の神楽(1708年)が最も古い。関東で神楽が最も盛んになったのは18世紀中ごろである。小栗の太太神楽は寛延3年(1750年)、山城国愛宕郡三嶋神宮宮司と祇置大政所の市大進により内外大神宮、宮司小栗山城守宣政に伝授され、その後伊勢の神楽師の指導を受けて今日のように十二神楽(12場面)三十六座(36柱の神々)成立させた。
太太神楽は四つの構成で出来ている。第一部は幣の舞・神子舞・五行の舞・陰陽の舞など一座から九座まで、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)・伊弉冉尊(いざなみのみこと)への感謝の気持ちを表し、第二部は十座から十九座で邪気や悪霊を退散させ平穏を祈る舞でいわば五穀豊穣を願う舞である。第三部は二十座から二十八座迄で武人神の功績を賛美することにより、天下泰平を招来する舞が行われる。第四部は二十九座から三十六座までで、福の神を招き新生命を育む巫女への願いの舞と、大神宮の安寧を祈願する舞が奉納される。尚、番外として八岐大蛇(ヤマタノオロチ)退治の黙劇が演じられる。これは大正時代に神楽師が作ったものと言われている。楽人は太鼓、大太鼓、笛、舞人は狩衣、大口袴、姫衣装、烏帽子、赤熊、頭巾の衣装をまとい、榊、鈴、弓、幣、短剣などを持ち、神の依代として手を高く挙げて舞う。舞の担い手は講中の人が交代で楽人、舞人を行う。神楽は毎年春4月20日(前日曜日)秋11月10日(前日曜日)に奉納される。

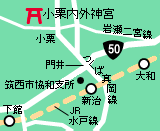
【おぐりないげだいじんぐうだいだいかぐら】2015/06/05掲載
嬥歌と夫女之石(かがいとふじょがいし)
つくば市筑波ふれあいの里
東国で、専ら嬥歌(かがい)と呼ばれる行事は、一般に云う歌垣(うたがき)と別なものではなかった。これは農作物の豊穣を祈願する宗教的儀礼に深く関わった行事であった。古代では男女の性交も、産霊(むすび)の神の力を発揚させるものと信じられていた。産霊とはものを産み出す霊力そのもので、人間の誕生にもこの神の力が関わっていたのである。新生児は神からの授かり物と観念され、男の子を「ムス子・息子」、女の子を「ムス女・娘」と称するのは「ムスビ」の神の子と考えられたからである。
同様に、穀物を産み出し増殖するにも神の力が必要であった。この穀物を産み出す神、つまり穀霊は特に「うかのみたま」と尊称されていた。「うか」は神聖な穀物の意で、「みたま・御魂」は「霊」同義である。因みに、伊勢神宮の外宮に祀る豊受大神は、まさに豊かな「ウカ」(穀物)を恵む豊穣の神である。記紀や万葉集などに伝えられる国讃(くにほめ)の歌は、すでに天皇や豪族層の領域支配の政治的な行事に変質しているが、その根底には、首長が共同体を代表して豊穣を祈願する行事が存在していた。そして、祝いの最後を締めくくるものとして・・夕闇迫る頃、そこに集まった男女が篝火を中心に嬥歌をおこなった。
男と女は、それぞれ別になり、ひとかたまりになって向かい合い、お互いを讃る歌を掛け合う。このように歌を掛け合うことにより歌垣と呼ばれたのである。同様に嬥歌も「掛け合い」に由来する言葉である。男は女の群れの中から目指す一人の女に求愛の歌を贈る。女性も受け入れる気があるならば、それに応える歌を返す。この求愛の歌のやり取りが歌垣だ。これが同意の合図となって、二人は手を取り合って嬥歌の列から外れ、暗闇に消えていく。勿論、最後まで相手の女性に恵まれなかった男性もいたはずである。
高橋虫麻呂の歌・・・筑波嶺に登りて嬥歌会せし日に作れる歌一首。
♪鷲の住む 筑波の山の 裳羽服津(もはぎつ)の その津の上に 率(あとも)ひて 未通女壮士(おとめおのこ)の 往(ゆ)き集い かがふ嬥歌に 他妻(ひとづま)に 吾も交らむ わが妻に 他(ひと)も言問え この山を 領(うしは)く神の 昔より 禁(いさ)めぬ 行事(わざ)ぞ 今日のみは めぐしもな見そ 言も咎むな。【万葉集巻九の一七五九】
注:場所は「裳羽服津」「夫女原(ふじょがわら)」の地と確定できる。
祭日は毎年6月中旬、但し『筑波誌』によれば、二月、八月とある。
と歌われる如く、この嬥歌の日の行為は神も禁止せず、人々もその情交を咎めなかった。だからこそ、激しく男女の情念が燃焼する、自由な恋の場所だったのである。その嬥歌は、筑波山のように夫婦の山の泉の湧く「裳羽服津」の場所が選ばれた。「裳」は女性の腰部に纏う衣装で、「ハキ・羽服(はき)」は着用の意であるから、恐らく筑波山の女峰(女神)陰部に当たる場所を指すものと解されている。筑波の山は男神と女神の抱擁の姿そのものと考えられていたから、恐らく優れて生殖の神と見なされていたのだろう。

【夫女之石】ここ夫女之原にある陰陽石ともいわれる奇石。その形が男女が並んでいるように見える為にこの名が付けられた。古代このあたり一帯で嬥歌が行われていたと伝えられている。
『筑波山名跡誌』によれば、「三里登りて絶頂よりも見ゆる。石の上に各桜木あり。二木相対して枝を交ゆ。斬る非情の木石までも陰陽不離の理を願わす。神の神徳たるべし」という。
『常陸国風土記』参照 2015/05/20掲載
筑 波 の 神
古老の話によると筑波の山にまつわる次のような話が伝えられている。
昔神の親神様が子供の神のもとに巡回していった。ちょうど駿河国の富士山に辿り着いた時、とうとう日が暮れてしまった。そのため、一晩泊めてくれるように富士山の神に頼んだ。この時、富士の神が答えるには、「新嘗祭をしていて、家中の者が罪や穢れを避けるため、身を清めています。今日だけはお願いですからゆるして下さい。」と申し上げた。それを聞いて、親神様は、恨み泣いておっしゃるには「とりもなおさず、私はお前の親である。どうして泊めてはくれないのか。お前が住む山は一生にわたって、冬も夏も年中雪が降り、霜が降り寒さが続き、人々は登らず、食物も供えるものもなくなる。」とおっしゃった。その上で、今度は筑波山に登って、親神様は泊まらせてくれと頼んだ。この時、筑波の神が答えて言うには、「今夜は新嘗祭ですが、しいて親神様にお仕えできないことはありません。」と申し上げた。そこで飲食物を用意し、敬い拝し、丁重にお仕えした。この時親神様はたいそう喜んで歌うには、「愛しいわが子よ、高く大きな筑波山よ、宇宙に等しく、太陽や月と同じように、永久に変わることなく、人々は筑波山に集まり祝い、食物は沢山に供えられ、いつまでも絶えることなく日に日に益々栄えて、千万年の後までも筑波山での楽しみは尽きないであろう。」とおしゃられた。このようなわけで、富士山はいつも雪が降って登ることもできなくなった。それに比べて筑波山は、人々が登り集まって歌をうたい舞ったり、飲んだり食べたりして楽しみ、今日まで絶えないのである。筑波の山にはこのような言い伝えがある有難い山なのである。
「万葉集」「古今集」などにも筑波山は歌にうたわれている。筑波山は神々の住む山である。それと同時に仏の山でもある。元来が日本の場合、神仏習合思想である。神が仏の現身かは別として、いずれにせよ神であり、同時に仏であることが多い。仏教の言葉に「山川草木悉皆仏」がある。筑波山は仏様の霊場、霊地であり修験道の聖地でもある。それ程に、筑波山は仏教に縁が深いのである。つまり、筑波山は仏の住む山でもある。だから、筑波山の別名を五台山、霊鷲山(りょうじゅせん)、栖鷲山(せいじゅせん)という。何れも仏教の聖地に因む別名である。『筑波山名跡誌』解説:桐原光明書参照 2015/05/09掲載