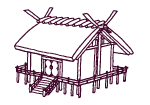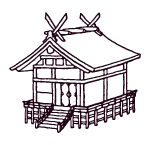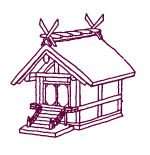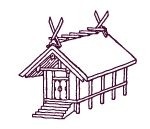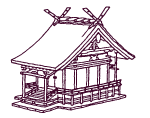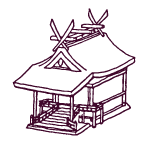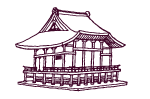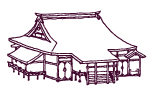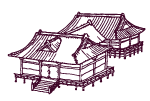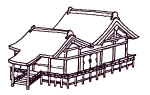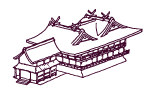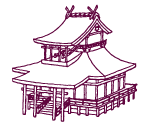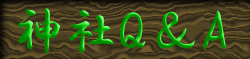 |
|||||||
|
|
|||||||
| Q.神社建築はどんなふうに発達してきたのですか? A:神社の中心は本殿ですから、神社建築も本殿の形式を本位に何々造と呼ばれます。 大体上古から奈良時代ぐらいまでの間は、建物のない神籬(ひもろぎ)式または磐座(いわくら)式の神社が多く稀に住宅風の建物を本殿とするものもあったようです。後者の最も原始型のものは、普通に天地根元造(てんちこんげんつくり)と呼ばれる掘立小舎式のものから生まれた形式で、直線式の極めて簡素な建物です。これから現在伝わっているような直線的形式の各種のものが生まれたのですが、これらは、間取りとか出入り口の関係で神明造・大社造・大鳥造・住吉造などの4つぐらいの形式に分けられます。 やがて飛鳥奈良時代に至って仏教建築が流行し、平安時代に入り真言宗・天台宗が興りますと、その影響を受けて神社にも寺院建築の風を採り入れ、一方では宮殿風の造りも加わって、曲線的形式が建築要素として加味せられ、種々な新様式が生まれましたが、特に流造は簡素なうちに森厳典雅な気分を良く表現しているので、次の鎌倉時代にも盛んに用いられました。 室町時代は群雄割拠の時代ですから、建築も各地方で思い思いに発達し、いろいろな形式が現れます。中でも桃山時代に起こった権現造は東照宮の建築に採用せられて有名になり、江戸時代に非常な発展を見せました。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
神明造り
(しんめいつくり) |
大社造り
(たいしゃつくり) |
大鳥造り
(おおとりつくり) |
住吉造り
(すみよしつくり) |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
流造り
(ながれつくり) |
春日造り
(かすがつくり) |
日吉造り
(ひよしつくり) |
祇園造り
(ぎおんつくり) |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
権現造り
(ごんげんつくり) |
八幡造り
(やはたつくり) |
吉備津造り
(きびつつくり) |
浅間造り
(せんげんつくり) |
|||||||||||||||
| Q.氏神(うじがみ)様って何ですか? A:日本中にたくさんおられる神様の中で、とりわけ私たちの日常生活に関係の深い神様、それが氏神様と呼ばれる神様です。氏神とはもともと、古代社会で血縁的な関係にあった一族がお祭りした共通の神様のことで、その一族の祖先神だったり、その一族に由緒深い神様だったりすることが多かったようです。 |
||||||||||||||||||
| Q.初宮参りってどういう意味があるんですか?
A:子供が生まれることを子が授かるとか、子を恵まれたとか申します。両親が作ったものではない。神様の思召しで、その御霊(みたま)を受けて生まれたのだという意味です。『人は神の子』という日本民族の伝統的な考え方に根ざしています。そこで子供が生まれると氏神様に初めての御挨拶に参る。これが初宮参りです。
|
||||||||||||||||||
| Q.七五三詣について教えてください。
A: 11月15日に七五三と申して、女7才、男5才、男女3才の子供が着飾って氏神様に参拝する習わしがありますがこれは昔の髪置(かみおき)・袴着(はかまぎ)・紐落し(ひもおとし)などの祝いから起こった事です。 |
||||||||||||||||||
| Q.厄年について教えてください。
A:厄年というのは、人間の一生のうち厄難に遭遇するおそれが多い年齢のことをいいます。医学の発達した今日でもなお、忌み慎まなければならない年頃として、一般に根強く意識されています。 女性 19歳・33歳・37歳
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||