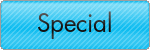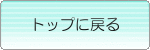◆マンマシーンデータ:ゾーリン・ソール

性能諸元
| 開発コード | RX-110 |
| 頭頂高 | 19.2m |
| 全高 | 20.8m |
| 本体重量 | 26.8t |
| 全備重量 | 60.2t |
| ジェネレータ出力 | 5,200kw |
| スラスター推力 | 68,000kg |
| センサー有効半径 | 18,000m |
| 装甲材質 | ガンダリウム・コンポジット |
武装設定
ニュータイプ87年11月号口絵
- 頭部は60mmバルカン砲2門
- ロング・フィン・ファンネル
- ファンネル・ミサイル
ニュータイプ91年3月号口絵
- Pak43A・・・エレクトロ・ケミカル砲の一種で、装甲貫徹力の高いMS-HEAT(多段成型弾)を超高初速で発射
ホビージャパン91年4月号「ガイア・ギア2D&3Dファイル」インスト
- Pak43A エレクトロ・ケミカルガン・・・装甲貫徹力の高いMS-HEAT(多段成形炸薬)弾を超高初速で発射する。

- ゾーリンソール・シールド・・・裏面にファンネル2基を搭載した攻撃用

- ゾーリン・ファンネル・・・νガンダムに装備されていたのと同様のフィン・ファンネルである。ただし構造的には進歩しており、機体もさらに小型化されている。本体は、プロペラントタンク兼ビームの発振誘導機能を持つ3枚のヒレ状の部分と推進機、エネルギーCAPから構成され、収納状態から攻撃形態へと自在に変形する。当然Iフィールドを利用したバリアー発生させるサテライトとしても使用可能だがミノフスキーバリアー装備のゾーリンソールでは実際に使用する局面は少ないだろう。

搭乗パイロット
小説版
- アフランシ・シャア(1巻7章)
- マドラス&ジョー(3巻2章)
- メッサー・メット(3巻5章)
- ジョー・スレン(5巻3章)
サウンド版
- ケラン・ミード(10話)
- アフランシ・シャア(12話)
使用状況
小説版
シャア・コンテニュー・オペレーションの責任者か、ズィー・ジオンの責任者がシャア・アズナブルの再来たるアフランシのために用意した機体。操縦はアームレイカーで行う。高速戦闘を重視したドハディなどに比べ、汎用性能には欠けるが細かい動きが正確であり、地球環境での使用を考慮したミノフスキー・フライトの決め細やかさも併せ持っている。1機しかしか存在しないワンオフマシンで、バァム・ゼーゲンによってホンコンの廃ビル内に保管されていた。バァム・ゼーゲンから「遺産」としてこの機体を託されたアフランシは、シャトルジャックにこの機体を利用して宇宙へと上った。ヘラスに入港した後、アフランシは解体を命じたが、ミランダは万が一のために解体はせず、コロニーの外に出すことで妥協した。アフランシが31の2乗と合流した後はメタトロンのマンマシーンとして利用され、クリシュナ奪還作戦の際にはジョーとマドラスが複座で乗り込んだ。その後は多少反応の鈍い機体と荒い気性とのマッチングからメッサーの機体となり、マハ追撃作戦でも使用された。ホンコン・マハのギッズ・ギースとの交戦で左腕を失ったあとは、メタトロンの制式機種ではないため修理されることもなく放置されていたが、クリシュナを探しに出たジョーがこれに乗り出撃。クリシュナと偶然同行していたエヴァリーを救助するものの、アフランシ部隊への帰途上でウルのギッズ・ギースと対戦し、ろくに武器の無い状態で善戦するも撃破された。(初出 1巻7章)サウンド版
メタトロンが開発・製造した量産型マンマシーン。やや旧型の機体だが、操縦系統はガイア・ギアαと大差は無い。主にヘラスで製造され、マハによる弾圧の際にほぼ全ての機体が持ち出されたが、一部は港近くの工場に隠匿され、逮捕されたアフランシ奪還のためガウッサを強奪したジョーたちを支援するケランがその隠匿されていた機体で出撃した。その後、コロニー外部でマハのガウッサ第4中隊と交戦状態に陥るが、ニュータイプとして目覚めたアフランシがパイロットとなりただ一機で全滅させる。マハ追撃作戦でも使用され、ケランがゾーリン・ソール第二小隊の小隊長となった。が、ウルに気をとられたアフランシの独断専行が原因で3機が撃墜された。その後ただ1機となったケランの乗機として戦うが、ヌーボ・パリでの迎撃戦にてジョーのドハディをかばって撃破された。(初出 10話)機体解説
サウンド版2巻ライナー
 マンマシーンとしてはすでに旧式の部類に入るゾーリン・ソールだが、その堅実な基本設計を活かし、幾度もの機体アビオニクスの改修を受けており、現在でも新型機種に比べて遜色のない性能を持つ優秀なマンマシーンである。”ミノフスキークラフト”による飛行が可能な上、”サイコミュ・システム”を搭載し、脳波誘導兵器”ファンネル”の運用も可能な高級機である。
マンマシーンとしてはすでに旧式の部類に入るゾーリン・ソールだが、その堅実な基本設計を活かし、幾度もの機体アビオニクスの改修を受けており、現在でも新型機種に比べて遜色のない性能を持つ優秀なマンマシーンである。”ミノフスキークラフト”による飛行が可能な上、”サイコミュ・システム”を搭載し、脳波誘導兵器”ファンネル”の運用も可能な高級機である。
小説版3巻口絵
改修型ゾーリン・ソール ミノフスキー・モーターの搭載など、かつては革新的な性能を誇ったゾーリン・ソールも、急激な発達を続ける技術革新の波には勝てなかった。しかし、生産に膨大なコストを要するマンマシーンを、そうおいそれとは更新できない。そこに改修型の意味があるのだ。
最初は連邦軍モビルスーツの影響が色濃かったゾーリン・ソールだが、改修を受けるに従ってしだいにメタトロン独自のフォルムを強めてきた。改修の基本はここでも装甲の強化。常に繰り返されることだが、実戦はまず兵器の装甲を、平時の想定を超えて強化させるものである。
ミノフスキー・モーターの搭載など、かつては革新的な性能を誇ったゾーリン・ソールも、急激な発達を続ける技術革新の波には勝てなかった。しかし、生産に膨大なコストを要するマンマシーンを、そうおいそれとは更新できない。そこに改修型の意味があるのだ。
最初は連邦軍モビルスーツの影響が色濃かったゾーリン・ソールだが、改修を受けるに従ってしだいにメタトロン独自のフォルムを強めてきた。改修の基本はここでも装甲の強化。常に繰り返されることだが、実戦はまず兵器の装甲を、平時の想定を超えて強化させるものである。
小説版4巻口絵
ゾーリン・ソール・ドライヴ・ユニット 戦闘兵器には2つの考え方がある。ひとつは単体でできる限り最高の性能を追求するもので、一種の理想主義的兵器。もうひとつはより現実的な考え方で、兵器の性能はそこそこに抑え、任務に応じてユニット式に性能を強化するもの。今回は後者の一例。
ドライヴ・ユニットは瞬間的な運動性を向上させるとともに、巡航性能の向上にも威力を発揮する。ただし外部は投棄は困難。
戦闘兵器には2つの考え方がある。ひとつは単体でできる限り最高の性能を追求するもので、一種の理想主義的兵器。もうひとつはより現実的な考え方で、兵器の性能はそこそこに抑え、任務に応じてユニット式に性能を強化するもの。今回は後者の一例。
ドライヴ・ユニットは瞬間的な運動性を向上させるとともに、巡航性能の向上にも威力を発揮する。ただし外部は投棄は困難。
ニュータイプ87年11月号口絵
モビルスーツ「ゾーリン・ソール」。その開発の経緯は謎だが、バアム・ゼーゲンの言葉を借りるなら、「アフランシのために用意された遺産」である。シャア・アズナブルやアムロ・レイが活躍した時代よりはずっと後に造られた機体なのは、その20メートル大のサイズにもかかわらず、機体内部にミノフスキーモーターを持つことで明か。本来はホワイトベースのような大型戦艦にのみ搭載が可能だった機関で、暫定的ながら反重力を発生させることが出来る。これまでモビルスーツは、大気圏内ではド・ダイなどのサポート・メカに乗らなければ飛行できなかったが、ミノフスキークラフトとバーニアの併用により自力飛行が可能になった。ジオン軍系の機体だが、部分的には連邦軍製モビルスーツを参考にしているところも多い。- 頭部には60mmバルカン砲を2門装備。センサー類が集中しているため額と後頭部は2重の装甲に覆われている。
- 両肩と腰、脚にはミノフスキー粒子による力場を利用したミノフスキークラフトがあり反重力飛行が可能だ。
- ロング・フィン・ファンネル。モビルスーツ本体を離脱した後に変形し、高機動の小形ビーム砲となる新兵器。
- 背中には3基のブースターがあり、強力な推力を発生させる。両肩から後方に伸びているのはロング・フィン・ファンネル。
- 腰の周りについているのはファンネル・ミサイル。サイコミュ操作により、直接目標物に激突、破壊する。
- 腰にも両肩と同じくロング・フィン・ファンネルが装備されている。指向性ビームを発し、目標物を破壊する。
ニュータイプ91年3月号口絵
ゾーリン・ソール ウエポン・システム 汎用兵器(幅広い任務をこなすことのできる兵器)としてのマンマシーンの機能を最大限に発揮させるためには、完備したウエポン・システムを開発することが必須の条件である。特に、攻撃兵器、および防御システムが重要なのはいうまでもない。- ゾーリン・ソールの攻撃兵器のひとつPak43A。いわゆるエレクトロ・ケミカル砲の一種で、装甲貫徹力の高いMS-HEAT(多段成型弾)を超高初速で発射する
- アクティブ・ダンパー機能をもつシールド
ホビージャパン91年4月号「ガイア・ギア2D&3Dファイル」インスト

 ゾーリンソール機体解説
「シャア存続計画」を推進するズィーオーガニゼイションによって、ホンコンの廃ビルにモスボール状態でほぼ一世紀に渡って隠匿されていたゾーリンソールは、U.C.0110年ロールアウト、U.C.0093年の「シャアの反乱」以降開発されたペーネロペー、Ξガンダムといった一連の第5世代MSと呼ばれる機種の発展型として、アナハイム社の主導で開発された。サイコミュ、ファンネル、ミノフスキークラフト、ミノフスキーバリアーといった当時の最先端技術をすべて盛りこんだ量産性を度外視したといってもいいような超高級、高性能機である。U.C.0105年の「マフティー動乱」以降、反地球連邦政府運動も表面的には鎮静化し、大きな戦乱のなかった当時の状況のなかで、新型機の開発計画は縮小される傾向にあったにも関わらず、こういった機体の開発が行われた裏には、ズィーオーガニゼイションによる連邦政府、アナハイム社双方への働きかけがあったと推測される。事実、ソーリンソールの開発時期にあたるU.C.0110年頃には、MSの運用コストの増加から機体の大型化、高級化に対して見直しを計るべきとする意見が連邦軍内においても主流となりつつあり、これ以降こういった超高級機の開発はかなり長期間に渡って中断している。ゾーリンソールも結局のところ試作にとどまり正式採用は見送られていることから、この機体の開発自体「シャア存続計画」のプログラムの一環としてあらかじめ組み込まれていたとみるのも、あながち穿った考えではないだろう。メタトロンに収容されてからも、機体アビオニクスの換装、サイコミュの調整等の改修を受け実戦参加している。これはゾーリンソールの、古めかしいながらも堅実な基本設計の優秀さを示しているが、このことから、ほぼ一世紀にわたり地球圏の科学技術には抜本的な革新がなく、中世的な停滞の様相を呈していたことが伺える。
ゾーリン・ソール武装解説
ゾーリンソール機体解説
「シャア存続計画」を推進するズィーオーガニゼイションによって、ホンコンの廃ビルにモスボール状態でほぼ一世紀に渡って隠匿されていたゾーリンソールは、U.C.0110年ロールアウト、U.C.0093年の「シャアの反乱」以降開発されたペーネロペー、Ξガンダムといった一連の第5世代MSと呼ばれる機種の発展型として、アナハイム社の主導で開発された。サイコミュ、ファンネル、ミノフスキークラフト、ミノフスキーバリアーといった当時の最先端技術をすべて盛りこんだ量産性を度外視したといってもいいような超高級、高性能機である。U.C.0105年の「マフティー動乱」以降、反地球連邦政府運動も表面的には鎮静化し、大きな戦乱のなかった当時の状況のなかで、新型機の開発計画は縮小される傾向にあったにも関わらず、こういった機体の開発が行われた裏には、ズィーオーガニゼイションによる連邦政府、アナハイム社双方への働きかけがあったと推測される。事実、ソーリンソールの開発時期にあたるU.C.0110年頃には、MSの運用コストの増加から機体の大型化、高級化に対して見直しを計るべきとする意見が連邦軍内においても主流となりつつあり、これ以降こういった超高級機の開発はかなり長期間に渡って中断している。ゾーリンソールも結局のところ試作にとどまり正式採用は見送られていることから、この機体の開発自体「シャア存続計画」のプログラムの一環としてあらかじめ組み込まれていたとみるのも、あながち穿った考えではないだろう。メタトロンに収容されてからも、機体アビオニクスの換装、サイコミュの調整等の改修を受け実戦参加している。これはゾーリンソールの、古めかしいながらも堅実な基本設計の優秀さを示しているが、このことから、ほぼ一世紀にわたり地球圏の科学技術には抜本的な革新がなく、中世的な停滞の様相を呈していたことが伺える。
ゾーリン・ソール武装解説
Pak43A エレクトロ・ケミカルガン
装甲貫徹力の高いMS-HEAT(多段成形炸薬)弾を超高初速で発射する。
本体の上下に開く部分は、砲身の強制冷却と余剰電力の放電用。
ゾーリンソール・シールド
ミノフスキーバリアーを装備するゾーリンソールの携行するシールドは補助ジェネレータを内蔵するファンネルラックといった性格のものであり、防御用の盾としての役割は補助的、付随的なもので、むしろ攻撃用の兵器としての機能がメインである。ファンネルは設定のように裏面に2基オフセットされる。当然高価な装備であり、通常のシールドのような使い捨ての消耗品ではない。
シールド、ファンネル射出ギミック
図のように後端部がひらきファンネルを放出する。ファンネル自体の容量がたいへん小さいので、ローテーションで回収し、エネルギーチャージを行わなければならないため、ファンネルシステム搭載機にはこういった一種の母艦的機能が必要とされる。
メガビームを発射するファンネル
カウンタースラストを噴射してバランスを保っているファンネルそれ自体が1個のメガ粒子砲である。
ゾーリン・ファンネル
νガンダムに装備されていたのと同様のフィン・ファンネルである。ただし構造的には進歩しており、機体もさらに小型化されている。本体は、プロペラントタンク兼ビームの発振誘導機能を持つ3枚のヒレ状の部分と推進機、エネルギーCAPから構成され、収納状態から攻撃形態へと自在に変形する。当然Iフィールドを利用したバリアー発生させるサテライトとしても使用可能だがミノフスキーバリアー装備のゾーリンソールでは実際に使用する局面は少ないだろう。

腕部多目的ラッチ
シールド等のオプション装着時には、腕のサブ・スタビライザーをブロックごと取り外す。
ミノフスキークラフトとミノフスキーバリアー
ガイア・ギアαやゾーリンソールにも搭載され、この時代、新型マン・マシーンの装備として不可欠といってもよいが、「ミノフスキークラフト」と「ミノフスキーバリアー」の機能である。これらはみな、「ミノフスキー物理学」の応用技術であり、「ミノフスキー粒子」の存在なくしては有り得ないものである。ミノフスキー粒子は静止質量が殆どゼロで正か負の電荷を持ち、粒子間に働く電気力とTフォースによって正負が交互に立方格子状に整列したフィールドを形成する。これに作用してM粒子の相互作用を媒介し、斥力を生じさせるのがIフィールドであり、M粒子立方格子を圧縮したり、メガ粒子を偏向、収束することができる。ミノフスキークラフトは、このM粒子の性質を利用し、Iフィールドの斥力で制御されたミノフスキー粒子の立方格子構造で機体重量を支えているわけで、重量加速度を打ち消したり、慣性制御をおこなっているのではないため、いわゆる反重力推進とは違うが、それに近い効果を得ることができる。当初は戦艦、MAクラスにしか装備できなかったが小型化がすすみ、U.C.0104年にはMSサイズでも搭載可能なものが開発されている。ミノフスキーバリアーもIフィールドによるM粒子の制御を応用したものである。ミノフスキー物理学応用技術を利用した防御システムにはビームシールドがあげられるが、ビームシールドがビームサーベルの原理を防御に応用したものであるのに対し、ミノフスキーバリアーはメガ粒子兵器に使用されるエネルギーCAP技術の原理に近い。エネルギーCAPとは、励起された状態のM粒子をIフィールドで装置内部に封じ込めたもので、蓄積されたM粒子の立方格子を必要に応じて圧縮すると「縮退」し、正・反2つの粒子が融合して、メガ粒子となり、見掛け以上の質量を増大させる。この過程でM粒子の質量の一部が運動エネルギーに変化するため、メガ粒子に高い運動エネルギーを与える。その運動方向をIフィールドによって揃え、目標に対し収束放出するのがビームライフル等のメガ粒子兵器である。ミノフスキーバリアーでは機体を励起したM粒子の場で包み込んでしまう。つまりエネルギーCAP内部の状態を機体周囲の空間にフィールドとして維持し、その場における任意の座標でM粒子を瞬間的に「縮退」させ、メガ粒子が生成される際に発生するエネルギーで攻撃を減殺するのである。当然ビームシールドやメガ粒子砲に比べてはるかに大きな電力を常時消費するために大出力のジェネレータが不可欠であり、システム自体も極めて高価で複雑であるが、全方位に対する防御が可能というメリットがある。ミノフスキークラフトもミノフスキーバリアーも機体周囲のM粒子の場をIフィールドで制御する点が共通しており、システムを大部分共有できることから、ゾーリンソールをはじめガイア・ギアα、ブロンテクスター等両方の機能を兼ね備えている場合が多い。